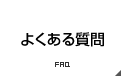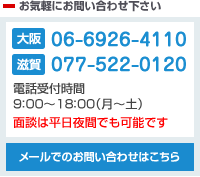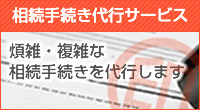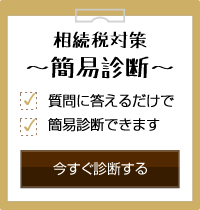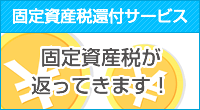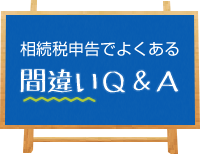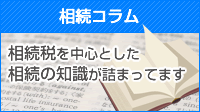![]()
- 大阪オフィス
- 〒530-0012
大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F - 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
- 滋賀オフィス
- 〒520-0051
滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F - JR大津駅から徒歩2分
![]()

大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
- 垂水区、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
- 右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
- 大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
- 上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
その他のエリアについてもweb面談等で対応いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
コラム
相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
ぜひ一度ご一読ください。
ぜひ一度ご一読ください。
贈与に関するコラム
暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選択すべきか
目次
1.税制改正による生前贈与への影響
相続税対策の中で生前贈与は最もポピュラーな方法です。従来は暦年贈与による贈与が一般的でしたが、令和6年税制改正により、暦年贈与は相続税の生前贈与加算の対象期間が相続開始前3年から7年に延長され不利な取り扱いに変更されました。 逆に相続時精算課税については基礎控除110万円が別途設けられ、基礎控除以下の贈与ついてはその期間に関係なく、相続財産の持ち戻し対象から外れることになり、有利な改正がされました。生前贈与において、暦年贈与と相続時精算課税による贈与のいずれを選択するかは、贈与者の年齢、遺産の金額、家族構成等によって、最適な方法は変わってきます。 今後、生前贈与の方法、贈与する金額・期間等の設定については、従来よりも選択肢が増えることになり、より慎重な判断が求められることになります。
2.生前贈与にかかる2つの税制
生前贈与には、主に「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがありますので簡単に解説します。2-1.暦年課税
暦年課税は通常の贈与税の課税方式のことで、その年の1月~12月までに受けた贈与に対して課税する制度です。受贈者一人あたり年間110万円まで基礎控除があり、基礎控除額の110万円を超えると超えた分に対してだけ贈与税が課されます。贈与者が死亡した場合の相続税については、直前7年以内の相続人等に対する贈与は110万円以下も含めて相続財産に加算されることになります。 ただし、令和9年1月1日以後の相続に関しては、経過措置として相続開始3年より以前の延長された4年間の贈与財産については、総額100万円まで相続税の課税価格に加算されません。
よって、暦年課税が向いているのは、贈与者の平均余命までの期間が長く、長期にわたって基礎控除を超える財産をコツコツと贈与したい家庭です。 年月をかけた贈与で効果的な節税を図ることができますが、贈与者が高齢で平均余命までの期間が短い場合には、相続前7年間の贈与は生前贈与加算として相続税の計算対象となるため、暦年課税による贈与の節税効果は見込めなくなります。 一方、遺産を相続する相続人以外(子の配偶者や孫等)に対する暦年贈与は相続税の生前贈与加算の対象外のため、加算期間を心配することなく贈与できます。なお、暦年課税の贈与税率は10〜55%の累進課税となります。
【贈与税の速算表 特例贈与財産の贈与】
特例税率・・18歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた財産に係る贈与税| 基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| ~200万円以下 | 10% | − |
| 200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超~ | 55% | 640万円 |
【贈与税の速算表 一般贈与財産の贈与】
一般税率・・上記以外の贈与財産に係る贈与税| 基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| ~200万円以下 | 10% | − |
| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超~ | 55% | 400万円 |
2-2.相続時精算課税
原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選択できる贈与税の制度です。 年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除が適用され、控除額までは贈与税が非課税となり、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。 贈与者が亡くなった際には、相続財産に過去に贈与した金額(年間110万円の基礎控除後)を加算して相続税を計算します。贈与税を支払っていれば、相続税と相殺します。 相続時精算課税は受贈者(もらった人)が贈与者(あげる人)ごとに選択できますが、一度選択すると暦年課税制度には戻れません。 令和6年改正前は110万円の基礎控除がなく、基本的に相続税の節税効果はないため、相続時精算課税による生前贈与を活用するケースは少なかったですが、税制改正で基礎控除110万円が設けられたことで、今後は利用が増加する見込みです。相続時精算課税の説明は相続時精算課税制度とはを参照してください。
相続時精算課税による贈与は、基礎控除110万円以下の金額については期間に関係なく相続財産に持ち戻さないので、暦年贈与のように7年間を待つことなく節税効果を得ることができます。
よって、贈与者の年齢が高く平均余命までの期間が短い場合でも、相続人に110万円の贈与をすることで節税できます。贈与者が亡くなった年の贈与については、相続日以降に相続時精算課税選択届出書を提出することで、精算課税制度を適用できます。 生前に精算課税制度を適用している方は少ないですが、相続税申告の節税方法として相続税申告の期限か翌年の3月15日のいずれか早い日までに届出をすることで、亡くなった年について110万円までは非課税とすることができます。
なお、遺産を相続しない子の配偶者や孫は生前贈与加算の対象外のため、あえて相続時精算課税を選択するメリットはありません。贈与する金額の選択肢が広い暦年贈与が良いでしょう。
「相続時精算課税選択届出書」の提出先
| 手続内容 | 提出先 | 提出時期 |
| 相続時精算課税を初めて選択するとき | 受贈者の住所地を管轄する税務署 | 贈与を受けた翌年の確定申告期間(2/1~3/15) |
| 相続時精算課税を贈与者が死亡した年に選択するとき | 贈与者の死亡に係る相続税の納税地を管轄する税務署 | ①贈与を受けた翌年の確定申告期間(2/1~3/15) ②相続開始を知った日の翌日から10か月以内 ※①または②のいずれか早い日 |
3.暦年贈与と相続時精算課税の比較
| 暦年課税 | 相続時精算課税制度 | ||
| 適用条件 | 贈与を受ける人 (受贈者) |
誰でも可 | 18歳以上の子、孫 |
| 贈与をする人 (贈与者) |
誰でも可 | 60歳以上の父母または祖父母 | |
| 届出 | 不要 | 「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出 | |
| 制限 | 贈与財産の種類、金額、贈与回数に特に制限なし | ||
| 贈与税 | 非課税枠 | 基礎控除 年間110万円 | 基礎控除 年間110万円 |
| 特別控除 累計額2,500万円 | |||
| 税率 | (累進課税)10%~55% | 非課税枠超過額に対して(一律)20% | |
| 申告 | 110万円を超えたら申告 | 110万円以下の贈与なら申告不要 | |
| ただし、選択する初年度は届出書を提出 | |||
| 相続税 | 贈与者が 亡くなった時 (相続時) |
相続開始前7年以内に受けた贈与財産については、基礎控除も含めて相続財産へ加算する。 (ただし、相続開始3年より前の4年間については総額100万円まで控除可) |
この制度を適用した年からの贈与財産全てを相続財産に加算 ただし、年間基礎控除は加算しなくてよい |
| 対象となる贈与財産に対しての納付済の贈与税は相続税額から控除 (贈与税>相続税の場合、精算課税は還付されるが暦年贈与は還付されない) |
|||
| 税率 | 相続税の税率(累進課税)10%~55% | ||
「暦年課税制度」
| メリット | デメリット |
| ・年間110万円まで非課税 ・贈与する金額を毎年柔軟に決めることができる |
7年以内の贈与は相続に加算される(改正後) ※基礎控除110万円も生前贈与の加算対象 |
「相続時精算課税制度」
| メリット | デメリット |
| ・110万円までは非課税で贈与税申告も不要 ・110万円までの贈与は期間に関係なく相続財産に加算しない ・一度に多額の贈与ができる ・将来値上がりする財産を贈与した場合、贈与時の評価額で確定されるので、相続税の節税になる |
・一度選択すると暦年贈与に戻せない ・受贈者が先に死亡した場合に相続税の負担が重くなる ・将来の相続で相続財産に持ち戻すため節税効果は限定的(基礎控除までの節税効果のみ) |
4.暦年課税と相続時精算課税を選ぶポイント
生前贈与の方法を検討するにあたり、暦年課税と相続時精算課税の選択は重要です。相続時精算課税制度と暦年課税のどちらが有利かは、贈与額や贈与期間、受贈者によって異なってきます。今回、事例の単純化のため、贈与する相手は相続人である子と相続人ではない孫とします。
大まかな考え方としては、親が高齢で贈与できる期間が短い場合、子については相続時精算課税を使った贈与が有利となります。親が多額の遺産をもち、贈与できる期間が長ければ、子は暦年贈与を選択することになります。 孫については節税対策として特に相続時精算課税を選択するメリットはないため、暦年贈与を選択します。
(1) 毎年110万円を繰り返し贈与する
両親や祖父母から毎年110万円以下の贈与を受ける場合は、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選んでも基礎控除内のため、その年の贈与税はかかりません。 よって、どちらでも同じように見えますが、贈与する相手が相続人の子の場合、生前贈与加算の対象のため7年経過しないと贈与の節税効果はなくなることになります。よって、子については、基礎控除110万円までは相続財産に持ち戻す必要がない相続時精算課税を使った方が有利となります。孫は生前贈与加算の対象外のため暦年贈与で問題ありません。
(2) 毎年110万円以上を繰り返し贈与する
例えば、毎年300万円ずつ贈与する場合、選択する課税方式により納める税金が変わります。子に対して暦年贈与をした場合、(300万円 – 110万円)×10%の贈与税19万円がかかります。 また、仮に7年後に相続が発生した際には、300万円×7年-100万円※=2000万円が相続財産に加算されることになり、結果的に100万円しか贈与したことになりません。 既に納付した贈与税は相続税に充当されます(贈与税>相続税の場合、還付はされません)。よって、子については相続時精算課税を使い110万円の基礎控除を活用した方が効果的だったと言えます。 一方、贈与する期間が長くなるほど、7年経過すると生前贈与加算の対象から外れるため、暦年贈与による節税効果が見込めることになります。 贈与する金額・期間、将来の相続財産の金額次第で結果は変わってくるため、ケースごとに具体的に計算する必要があります。
当オフィスでは詳細な生前贈与シミュレーションサービスを提供しているので、詳細はお問い合わせください。
※ 延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円まで相続税の課税対象外
5.暦年贈与と相続時精算課税の有利不利フローチャート
暦年贈与と相続時精算課税の選択フローチャートです。前提条件は、子は相続人で生前贈与加算の対象、孫は生前贈与加算の対象外です。| (1)受贈者が「子」か「孫」か? | → | 孫 | → | 暦年贈与 |
| ↓ | ||||
| 子 | ||||
| ↓ | ||||
| (2)親の余命が7年超か否か? | → | 7年以内 | → | 精算課税 |
| ↓ | ||||
| 7年超 | ||||
| ↓ | ||||
| (3)親の財産が多額か否か? | → | 多額ではない | → | 精算課税 |
| ↓ | ||||
| 多額 | ||||
| ↓ | ||||
| 暦年贈与 |
(1) 贈与する相手
贈与する相手が相続人となる子の場合、将来相続で遺産を相続するため、生前贈与加算の対象となります。 一方、孫は法定相続人でないため、通常であれば遺産を相続しません。よって、生前贈与加算の対象とならないため、相続時精算課税を選択するメリットは敢えてありません。 精算課税を選択すると、110万円以上の贈与をした場合、基礎控除を超えた金額は期間に関係なく相続財産に戻されるため、110万円超過分の節税効果は見込まれません。(2) 贈与者(親)の平均余命が長いか
贈与者(親)が7年後に亡くなった場合、暦年贈与だと子に対する贈与は生前贈与加算の対象となるため、節税効果がないことになります。 よって、親が高齢で相続まで長くないと見込まれる場合には、精算課税を選択して基礎控除110万円の贈与をするという考え方になります。孫については、(1)で記載した通り暦年贈与を選択することになります。親が後何年生きるかは誰にも分かりません。また、贈与をするには意思能力が必要ですが、今後、認知症が発症・進行し、贈与ができなくなる可能性もあります。 よって、生前贈与をシミュレーションする際には、現状の健康状態を踏まえた上で、厚生労働省から公表される平均余命が記載されている簡易生命表を参考にすることが多いです。
《 厚生労働省 簡易生命表 》
⇒ 令和6年簡易生命表(男)
⇒ 令和6年簡易生命表(女)
例えば、男性80歳の方の平均余命は約9年ですので、生前贈与加算を考慮すると子に対する贈与は相続時精算課税を選択することが多くなると考えられます。 今後、平均余命は年々伸びてはいますが、認知症で意思能力がないと判断されると贈与はできなくなるので、平均余命だけではなく、判断能力を維持できる年齢を考慮して贈与する期間を決めることになります。
(3) 遺産が多額かどうか
遺産が多額な場合、相続税の税率が高いので、贈与税を支払ってでも贈与をした方が、節税効果が見込まれるケースが多いです。 相続時精算課税による贈与の場合、基本的に110万円ずつ贈与することになりますが、それだと相続税の節税効果は限定的となります。いくら以上だと多額かは一概にはいえませんが、遺産1億円、法定相続人子3人の場合、贈与する相手が子3人、孫3人の6人だと、子は精算課税、孫は暦年贈与で年間110万円×6人=660万円無税で贈ることできます。 7年贈与した場合、4,620万円財産を圧縮できるので、相続税は基礎控除以下となりかからないことになります。一方、遺産が3億円だった場合、相続税は約4,000万円となり、相続税の限界税率としては30%になります。 このケースですと、贈与税の実行税率が30%以下の範囲で贈与税を払ってでも、暦年贈与で贈与した方が節税効果は見込めることになります。 仮に親の余命が7年のケースだと、子は精算課税で110万円、孫は暦年贈与で450万円贈与すると贈与税と相続税のトータルは約2,000万円となり、節税効果は2,000万円見込めることになります。
限界税率とは、相続税の速算表の税率のことをいい、実行税率は実際にかかる税金を財産(贈与金額)で割った率になります。
相続税と贈与税は、遺産の金額に応じて段階的に税率が上がる累進課税を採用しており、財産が増えると税金が高くなる仕組みになっています。
このように遺産が多額のケースでは、贈与税を払ってでも暦年贈与で贈与した方が節税できることになります。
6.まとめ
令和6年1月からの生前贈与の税制改正により、従来は暦年贈与による生前贈与が一般的で、相続時精算課税を選択するケースはほとんどなかったですが、今後は相続時精算課税を選択する家庭が多くなることが想定されます。 選択肢が増えるということは、検討事項が増えるということなので、今後最適な生前贈与の方法・金額を簡単に算定することができないケースが増えることが想定されます。当事務所では生前贈与シミュレーションに基づくコンサルティングにも対応しているので、相続税対策を検討される方はお問い合わせください。
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
- 大阪オフィス
〒530-0012
大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
06-6926-4110 - 滋賀オフィス
〒520-0051
滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
077-522-0120
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.